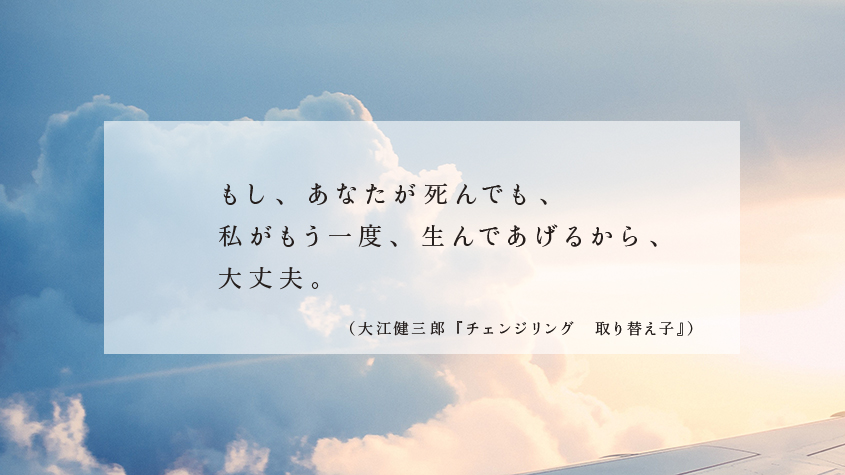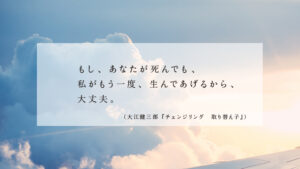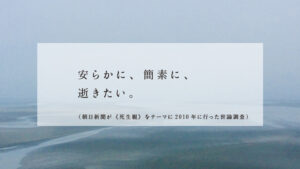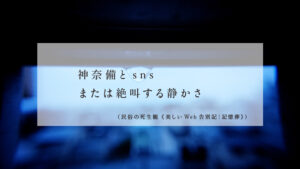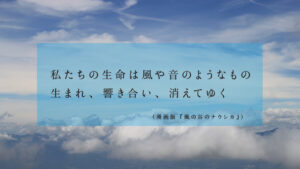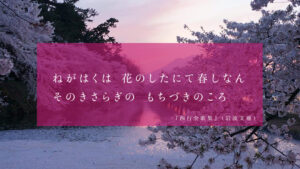日本の伝説や小説にみる「再生」の物語
人や魂の再生の物語は昔から多様なカタチで日本各地の民話や伝承に残されており、今でも小説などに語り継がれているものもあります。これらは6世紀の中頃に日本に伝えられたという仏教の輪廻転生思想の影響を受けつつ、日本独自の死生観や自然観と融合して、現代まで語り継がれてきたようです。
ところが、ここで取り上げる大江健三郎の作品に出て来る「重篤な子供と看病するその母」が交わす会話の「再生の物語」は、これだけを読むと、読者は母の言葉には戸惑ってしまいそうです。以下の少し長い引用は、強い雨の日に森に入り、彷徨った挙句の発熱のため、二日間大木のほこらに倒れているところを救出された、大江本人と思われる少年の話しになります。
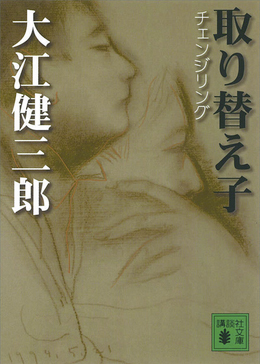 家に帰ってからも発熱はおさまらず、村の隣りの町から来てくれていたお医者さんが(私は夢の出来事のようにそれを聞いていたのですが)もう手当ての方法も薬もない、といって引き揚げてしまうことになりました。母だけが希望を失わず、看病してくれていたのです。そして、ある夜ふけに、熱もあり、衰弱してもいたのですが、それまでの、熱風につつまれた夢の世界にいるようだった状態から目がさめて、私は頭がはっきりしているのに気が付きました。
家に帰ってからも発熱はおさまらず、村の隣りの町から来てくれていたお医者さんが(私は夢の出来事のようにそれを聞いていたのですが)もう手当ての方法も薬もない、といって引き揚げてしまうことになりました。母だけが希望を失わず、看病してくれていたのです。そして、ある夜ふけに、熱もあり、衰弱してもいたのですが、それまでの、熱風につつまれた夢の世界にいるようだった状態から目がさめて、私は頭がはっきりしているのに気が付きました。
いまは田舎でもそうしたふうじゃありませんが、日本の家のやり方で、畳の床に直接敷いた蒲団の上に私は寝ていました。枕もとに、もう幾日も眠っていないはずの母が座り、私を見おろしていました。私は自分にもおかしく感じるほど、ゆっくりした小さな声を出して質ねました。
ーお母さん、僕は死ぬのだろうか?
ー私は、あなたが死なないと思います。死なないようにねがっています。
ーお医者さんが、この子は死ぬだろう、もうどうすることもできない。といわれた。それが聞こえていた。僕は死ぬのだろうと思う。
母はしばらく黙っていました。それからこういったのです。
ーもし、あなたが死んでも、私がもう一度、生んであげるから、大丈夫。
ー・・・けれども、その子供は、いま死んでゆく僕とは違う子供でしょう?
ーいいえ、同じですよ、と母はいいました。あなたが私から生まれて、いままでに見たり聞いたりしたこと、読んだこと、自分でしてきたこと、それを全部新しいあなたに話してあげます。それから、いまのあなたの知っている言葉を、新しいあなたも話すことになるのだから、二人の子供はすっかり同じですよ。
私はなんだかよくわからないと思ってはいました。・・・・・・・・
(大江健三郎『チェンジリング 取り替え子』講談社文庫p360-361)
これを読んだ時に頭をよぎったのは、死んだ人の霊魂は、一旦は近くの森の一番高い樹の頂に止まり、村の様子を見守っているが、そのうち村の女が妊娠したことを知ると、この魂は樹から飛び立ち、女が宿す胎児のなかに入り込み、生まれ変わって再びこの世に生を受ける、という再生の言い伝えでした。
おそらく、重篤だった少年の母親は、この言い伝えに希望を託し、少年用に言い換えて伝えようとしたのではないか、ところが、この言い方だとなかなか少年にも納得しがたい「もどかしさ」があったのではないかと、思った次第です。
*なお、この大江健三郎作品『チェンジリング 取り替え子』の「チェンジリング」は上記の短いエピソードのことを言っているわけではない。当作品のサブタイトル【Changeling:英】は、美しい赤ん坊が生まれると、子鬼のような妖精がかれらの醜い子供と取り替えるという民間伝承から持ってきており、この作品の全体を覆う大きなテーマになっている。この言い伝えはヨーロッパを中心に世界各地に見られ、チェンジリングとは、その残された醜い子のことを指すそうである。
死者の魂は、遺された人々の近くにとどまり、時々は帰って来てくれる
これら魂の再生の物語の前提には、私たちが霊魂の存在を信じている、少なくとも、それを希求しているという死生観を持っていることがあります。書籍からの引用が続きますが、『死とは何か 宗教が挑んできた人生最後の謎』(中村圭志 中公新書)では冒頭で、二元論(死後も霊魂は存在する)への懐疑として、次のような断り書きを置いています。
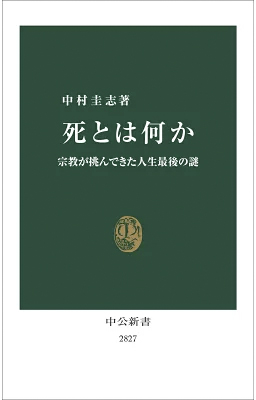 科学の基本的モデルは物理学などに代表される自然科学だ。一般的に言って自然科学者は、実在を物質的なものだと捉えている。すなわち、宇宙は時空間を占める物質的実在でできている。精神現象(心や意識や記憶や思考や感情)は、物質的身体の機能である。
科学の基本的モデルは物理学などに代表される自然科学だ。一般的に言って自然科学者は、実在を物質的なものだと捉えている。すなわち、宇宙は時空間を占める物質的実在でできている。精神現象(心や意識や記憶や思考や感情)は、物質的身体の機能である。
つまり、精神現象は物理的身体から独立した実在ではないので、死んで身体が崩壊すれば、そのときに精神現象は消失する。燃えるものが無くなったら火は消える。それと同じだ。
死についての哲学的講義録で有名なシェリー・ケーガンは、こうした《物質主義》的な見方を確定された事実と考えてはいないものの、しかし、今のところこれが最も一貫性のある、最も確からしい見方だとしている。絶対ではないが最も説得力がある、というのである(『「死」とな何か』)。たいていの自然科学者も、多くの哲学者もたぶんこれに同意すると思われる。
こうした《物質主義》に対して、ほとんどの宗教はもちろん、宗教とまでは言えない民間信仰の世界でも、例えばお盆の行事のように、亡くなった近しい人や先祖の霊魂らしきものをお迎えし、供養する気持ちを多くの人が今も受け継いでいるのも事実です。
日常の生活では、その日その日を生きて行くことに懸命な人も、正月やお盆、命日には亡き人や先祖のことを弔い偲ぶ、共に過ごす時間を作るという文化的な装置として、これらの行事が霊魂らしきものを媒介として定着したのも理に適っていると言え、日本人の死生観を象徴する一つの代表事例でもあります。
なかでも、死者の霊魂は最初は遺された者のごく近くにあり、次第に遠ざかりながらもお盆などには必ず戻って来てくれるが、長い時間の経過と共にそのうち名前のある故人ではなく「ご先祖様」のグループに分類されるという考え方は、極めて普遍的なレベルにあると思えます。
確かに、その面影がリアリティを持って眼に浮かび、追悼もできる故人とは、祖父や祖母までであることを思うと、それ以上の場合は「ご先祖様」としての認識になるのも頷けます。
「お父さん、お母さん、今も遥かな旅の途中ですか」
このように、故人の面影=霊魂のリアリティは、言い換えると、たとえ死んで身体が崩壊した後も、そこから飛び出した故人の霊魂らしきものはずっと存在して欲しいという遺された者の願望であり希求に他なりません。
私の場合も、両親が収まった墓の新しい石碑に「お父さん、お母さん、今も遥かな旅の途中ですか」と少し長い文章を彫ってしまったのは、死んでしまった二人だが、不条理に満ちたこの世界とは違うどこか別の宇宙に居続けて欲しいという個人的な願いを吐露したようなものです。ところが、そのうち子や孫へと時代が未来に進むにつれ、どこかの宇宙を旅する私の父母の霊魂らしきものも、時間と共に遺された者達から徐々に遠ざかり、リアリティも希薄になりながら「ご先祖様」として消えてゆくのかも知れません。もちろん、私もそう遠くはない日にその遥かな旅のプロセスに加わることになります。
最後に、戦後日本の文学評論、歴史や文化評論を代表する一人である加藤周一が、日本人の死生観について大変上手にまとめた一文があります。以下に紹介させてください。
第三に、死の哲学的なイメージは、「宇宙」の中へ入って行き、そこにしばらくとどまり、次第に融けながら消えてゆくことである。その三段階のなかで、「とどまる」期間は人によってちがうだろう。しかし、宇宙のなかへ「入る」またはそこへ「帰る」感情は、多くの日本人に共通だろうと想像されるばかりではなく・・・・
(加藤周一、M・ライシュ、R・J・リフトン共著『日本人の死生観』上・下2分冊 岩波新書1977年)
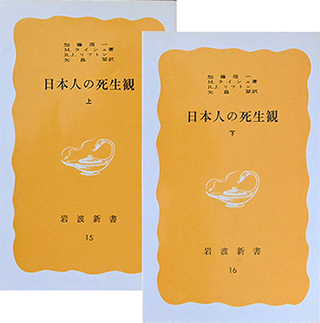
*加藤は共著『日本人の死生観』のなかでその特徴を4つにまとめています。上記はその3番目ですが、その他には《第一に、家族、血縁共同体、あるいはムラ共同体は、その成員として生者と死者を含む。死とは、少なくともある期間、同じ共同体の成員の第一の地位から第二の地位へ移ることを意味するに過ぎない。・・・第二に、共同体のなかで「よい死に方をする」ことは重要である。「よい死に方をする」とは、共同体の利益をそこなわず、共同体の定めた方式に従って死ぬことである。その方式の儀礼的な面は、徳川時代以後、主として仏教によっている。一般に「よい死に方をする」ためには、劇的ではなく、静かに死に対する。・・・第四に、「宇宙」へ入っていく死のイメージは、個人差を排除する。人間の死に介入する超越的な権威はないから、最後の審判はない。故人の生活の差によって、死後の世界でのあり方は変わらない。》
(『加藤周一著作集 7 』のp454-457から抜粋 平凡社)
*この本は今からおよそ50年ほど前に書かれているため、かつて全国津々浦々に存在していた共同体概念の崩壊という時代の変容は感じられますが、今読んでも違和感もない、上手にまとめられた普遍的な文章になっていると思われます。特に三番目の「死の哲学的なイメージは・・・・」から始まる一文は、哲学的でなくとも、実に意味深長な味わいを持っています。