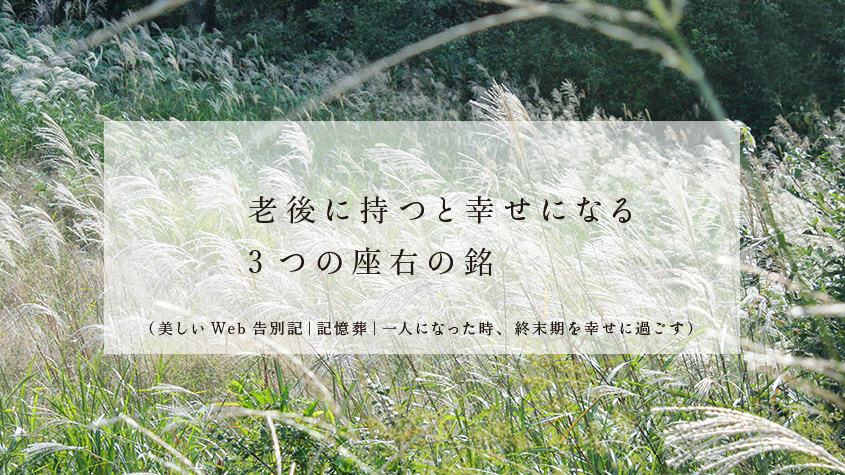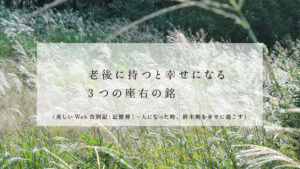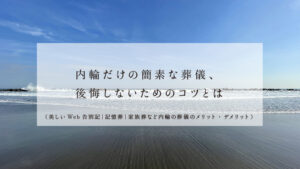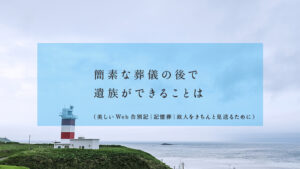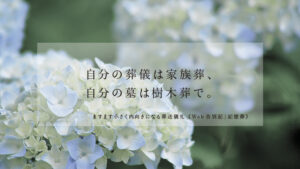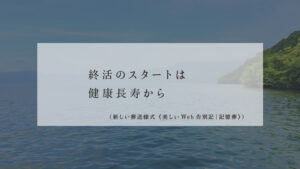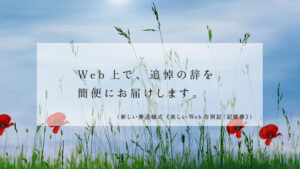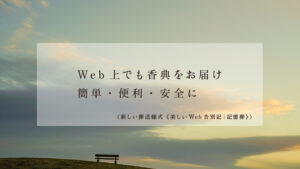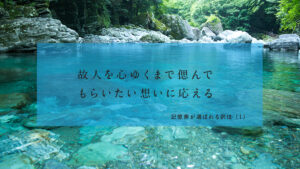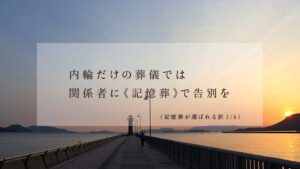メディアの注目記事から:
毎日新聞(電子版)政治プレミア:
2/26:孤独死は「悲惨なこと」か
7/01:死ぬ時は「一人で勝手に」?社会の不備
毎日新聞の一人暮らしについての記事を2本を紹介します。
一つ目は少し古いのですが、独協医科大学埼玉医療センターこころの診療科教授の井原裕さんへのインタビューで構成された《孤独死は「悲惨なこと」か》。単身で暮らす高齢者の増加とともに社会的な問題として扱われるようになった「孤独死」について語られています。人を社会的な生き物としての視点からみると、孤独死も自然な死に方の一つであり、一概に悲惨なことと決めつけはできないと言います。とは言え、実際には孤独死に局面すると、そこでは施設や病院での死とは違う様々な問題が派生するため、周囲のケアが欠かせないことはいうまでもありません。同時に、おそらくその直前までは他者の支えがなくても、一人で自立した生活が出来ていたのかも知れません。記事はこの課題を解決するためのいくつかのヒントを提示して終わっています。
二つ目も、愛知教育大学教授の中筋由紀子さんへのインタビューで構成された《死ぬ時は「一人で勝手に」?社会の不備》。「自分の死にどう向き合うか」という大変重い課題について。臨終から始まる葬送の儀礼は、少し前の時代までは家族や地域でサポートしていたのですが、「今はもうできなくなってしまい、けれども代わりにやる人はいないから、ぜんぶ自分でやらなければとなっている」のが現状であると中筋さんは言います。今は夫婦二人とは言っても、どちらかが先に逝くと遺された一人はどうやって死ねばいいのでようか。読んだ後で深く考え込んでしまいそうです。
2/26:孤独死は「悲惨なこと」か→Webサイトはコチラ
7/01:死ぬ時は「一人で勝手に」?社会の不備→Webサイトはコチラ
*青字部分をクリックすると別タブで配信ページが開きます。いずれも有料記事です。
生まれる時と死ぬ時、人は人の世話になるもの。
以前、コロナ禍の最中に公助の仕事をする国のトップが「自助>共助>公助」と3つの「助」に順番付けをしてしまったために話題になったことがあります。人は生まれる時も死ぬ時も一人では何もできません。普段、多くの大人は他人にはなるべく迷惑をかけないよう、自らを律した生活を送ろうとするものですが、経済的な困難や重い病気、とりわけ死という危機に瀕した時は、公的(および民間との共同)サービスに関わる場合もあります。
特に高齢者の一人暮らしの場合、普通に考えても国や自治体は彼らの生活につきもののリスクを少なくする様ざまなサポート体制を構築することが求められていますが、ようやく試験的・部分的に動き始めた段階で、多くはまだまだ今後の課題のようです。とは言え、近頃メディアで散見する「死後時間が経ってからの発見」という最悪の事態だけは避けるために、そこまで行かないように、公的サービスで、すぐにでも解決したいものです。
ちなみに、現在の日本の一人暮らしは2,000万世帯と言われています。この数字は、日本で最も多い世帯形態になっており、総世帯数の約4割以上を占めて過去最多に。その内訳は ➀ 就職・進学での都市部への移動による20〜30代 ➁ 非婚化や離婚の増加による40〜50代 ➂ そして急増しているのが配偶者との死別や子供との別居により一人となった高齢の単身者です。
一人暮らしの高齢者(65歳以上)は2020年の国勢調査では約670万人。19人に1人の割合*となっており、今後も増え続け、2040年には約4割に達すると予測されています。今は夫婦で暮らしていても、子供達と一緒でもゆくゆくは多くの人が一人暮らしを強いられる可能性があります。
*参照:nhketv「ナンブンノイチ」(24)19分の1のヒトって?ひとり暮らしの高齢者
そこで、一人になった時、どんなことが必要なのか。そして人生の終末を無事に乗り越えるためにはどういう方策があるのか。考えてみたいと思います。
一人暮らしは、もはや他人事ではなく
繰り返しになりますが、現在の日本の単身世帯数は約2,000万世帯。総世帯数の4割を占め、最も多い世帯形態になっており、その内訳は以下の3つに大別されます。
➀ 就職・進学での都市部への移動による20〜30代の若い層
➁ 非婚化や離婚の増加による40〜50代
➂ そして急増しているのが配偶者との死別や子供との別居により一人となった高齢の単身者です。
➂ の高齢者単独世帯は以前から増加の一途をたどっており、上述のように5年前の2020年には737万世帯(65歳以上)に達しています。この傾向は今後も続くようで、2033年には全世帯の平均人数が初めて2人を割り込み、2050年には単身世帯数が全体の約45%を占めるまでになると推測*されています。
*国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」から抜粋
高齢単身者の増加傾向は、地方よりもむしろ東京をはじめとする都市部の方がその数においても著しいと言われています。そんな状況を突きつけられると、高齢単身者の問題はとても他人事ではなさそうです。
一人暮らしの高齢者にとって、家族が同居・近居であればまだ安心ですが、家族などのサポートが難しい場合には、元気なうちから、行政の福祉の窓口(地域包括支援センター*など)に相談をしておくことが推奨されています。
*地域包括支援センター:高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、介護・保健・福祉の専門職が連携して総合的な相談・支援を行う公的な機関。最寄りの市役所などで問い合わせが可能です。
行政の窓口で、一人暮らしの高齢者サポート事業の内容を確認し、介護や福祉はもとより(特に身寄りがない場合の)自らの葬儀について直接の手続きやサポートはできませんが、これらに関する必要な情報の提供や関連の専門機関への橋渡しも担ってもらえる場合もあります。
以上のように、行政の窓口相談から始まって、信頼できる行政書士や司法書士など複数の候補を自分で選び、終活サポート業務の専門家に相談してみるなどの終末期の準備を始めるのも決して無駄ではないでしょう。
一人暮らしをシミュレーション
老後を夫婦二人で暮らしていても、どちらかが亡くなると単身者になり、子供など身近な親族もいない場合の遺された単身者は、一人で*自らの終末期を準備し、終活サポート行政窓口や専門の業者にあらかじめ自らのプランを委託しておく必要があります。
*可能な限り「ウマが合う」生涯の友と一緒になって相談し行動できると、より自分に見合った終末期を迎えることができるのではないでしょうか。その意味でもお互いを気にかけ合う「長続きのする友情」をできるだけ多くの親友と、今のうちから育てておくことも大切ですね。
特に、兄弟も子供もなく、身近な身寄りがない場合は、死後事務委任契約や見守りサービスなどを活用し、安心して生活を送れるように準備することが重要です。
高齢単身者の終末期の「葬儀」に至るまで、そこには様ざまな課題が横たわってきます。一番はお金の問題。将来、食事や洗濯、掃除などの日常生活が介護サポートを加えても自力では不可能になった場合、施設に入る費用はどのくらい必要でどう工面するのかを、自らの状況に合わせて想定しておくことも必須です。
第二は、健康を終末期まで持続し自活するためのプランを建てること。健康/不健康は、一番目のお金の問題と密接に関わってきます。今は健康でもそのうち次第に歩けなくなり、いつも間にか寝たきりになるような事態は極力避けたいものです。ここでも、上述のように「ウマが合う」仲間がいるといいようです。
この他にも一人暮らしの終活には、部屋のなかを整理整頓、医療や介護の問題、財産管理、身元保証人を誰にするか等々、多方面にわたりますが、最後に、これだけは欠かせないという課題として「これから自分は何を目的に、どのように生きて行くのか」。この漠然とではあるが、ひとつの目標や目的みたいなものを発見し、日常生活のルーティンを生きがいとして備えることができると、終末期までのプロセスもより充実できるのではないでしょうか。
老後のモットー3例、モノは捨てる・台所では食事を作る・外に出て少しだけ散財する
懐にも心にも余裕がある一人暮らしの老人の場合は、『月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。』を一度じっくりと自分で味わってみるためにも(できればウマが合う友と)旅に出ることがお勧めですが、ごく一般的で当たり前の人生を送ってきた私たちは、起床して枕元のスタンドのヒモを引いて眠りにつくまでの一日一日の日常の中で、例えば、次の三つのことを実践するだけでも満足度がアップするようです。
① 何時も住居は整理整頓を心掛け
身の回りのモノは必要の有無を判断し、断捨離の心意気で過ごす。モノを捨てられなくなる(モノの取捨選択ができず、片づけられなくなる)と、精神的な劣化の可能性があるそうです。これに、定期的な大掃除を付け加えると完璧です。
② 基本の三食*は台所で賄う
西洋のことわざ「朝は王様のように、昼は貴族のように、夜は貧者のように食べよ」という教えがあるそうです。これは、朝から始まって夜には寝るというヒトの一日の行動に適った食生活の例えのようです。老後の王様にはハムエッグ付きの朝食で十分だと思われますが、とにかく自分で作った料理が美味しいと、それだけで人生は幸せになります。時々は弁当や菓子パンなどに頼ることがあっても、やっぱり自分で作った方がよほどウマいと思えるうちは大丈夫だそうです。
*追伸:07/31の電子版「毎日メディカル」に《もう「1日3食」は卒業しよう! 血糖値の乱高下を防ぎ、脳の老化を撃退する食トレーニング》という衝撃の記事(有料)が掲載されました。これによると「ちょこちょこ5食」が、体にはより優しいそうです。→ 詳しくはコチラ
③ 目的をもって外出してみる
日頃の地元の商店街へ食材の買い物とは違って、たまには私的な目的を作り、電車やバスを乗り継いで目的地まで出かけてみましょう。その際、普段着とは少し違うお出かけファッションも考慮すると楽しさも倍増するかも知れません。いろいろと悩んだ末のファッション・スタイルに身を包み、映画でもコンサートでも美術館でも、自然に囲まれた公園でも好きな所を訪れてみるのも嬉しいものです。他にも、日頃利用する近くの本屋さんではなく、地域で一番大きい書店にわざわざ行ってみたりと、友達と待ち合わせて遊ぶのもQOL(Quality of Life:生活の質)を高めてくれそうです。