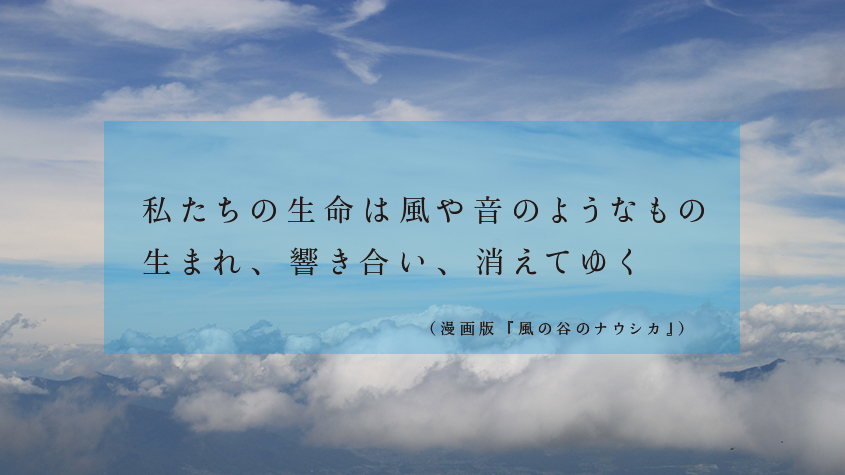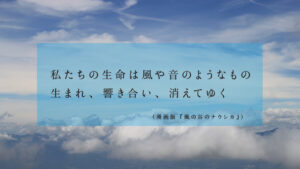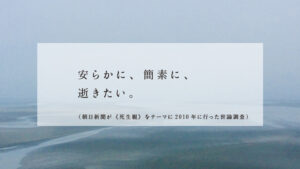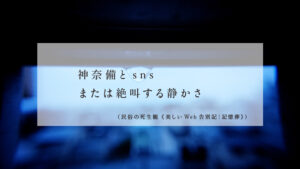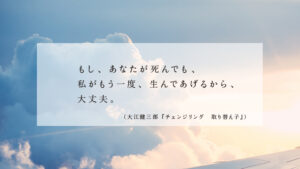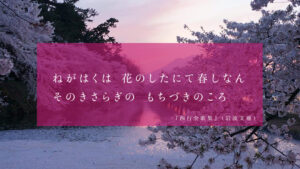宮崎駿は、漫画版『風の谷のナウシカ』で

かつてのコロナ禍のさなか、nhkBSでシリーズ「コロナ新時代への提言」が3回にわたり放映されました。
その2回目は宮崎駿の漫画版『風の谷のナウシカ』を共通のテキストにして福岡伸一+藤原辰史+伊藤亜紗の3人それぞれが、文明とテクノロジー、疫病の関わりについて現代の光と陰、特にその病巣のひとつ=パンデミックに対する心構えみたいなものを『風の谷のナウシカ』の様々な場面をを引用しながら、語り合ってくれる内容になっています。その番組のなかで、次のようなセリフが囁かれる場面が出てきます。
*漫画版『風の谷のナウシカ』(全7巻・徳間書店)の物語のプロセスは、ハッピーエンドの結末の映画版とは異なり、人類の科学技術の進展がもたらす破局的な禍いを通して、暗い未来をも示唆する宮崎駿の渾身の警告の書ともいえます。
私達の生命は、風や音のようなもの・・・生まれ、ひびきあい、消えてゆく。
(nhk番組 BS1スペシャル「コロナ新時代への提言 福岡伸一×藤原辰史×伊藤亜沙」より)
このナウシカの呟きは、人の一生をたった一行にまとめた、これを聴く者によっては、いかにも虚無的な響きを持つ多分に東アジアの稲作民族に特有な自然観を反映した表現だとも思われます。また、それにしても、これまでそうやって「消えて」行った私たち人の生命の数は、いったいどれほどになるのか想像もつきませんが、イギリスの精神科医Robert Wilkins(ロバート・ウィルキンズ)の著作には以下の記述があるのを見つけました。
これまでの人間の歴史で、すでに何十億もの人々がこの世から去り、彼らは悲しまれず、記録にも残らず、人々から忘れ去られてしまっている。また、この先数え切れないほどの人間がそうなっていくはずだ。
(『死の物語 恐怖と妄想の歴史』p214/ロバート・ウィルキンズ/1990年/原書房)
こうやって、人は次々と「忘れられてしまっている」一方で、にもかかわらず。人は生前はそれを大変恐れていると、次のように続けています。
死後も人々の記憶にとどまりたいという欲求、逆にいえば、死後忘れられてしまうことに対する恐怖は、人間をとりわけ不安にさせる要素の一つだ。いまから1世紀もたてば人々から忘れられてしまうと想像して不安にならない人間がいるだろうか、自分は元から存在していなかったかのようになってしまうのだ。我々のほとんどは、そうした考えに強い不安を抱く。
大抵の人間の場合、孫の代までは覚えられているが、曾孫の代になると忘れられてしまうものなのだろう。
(『死の物語 恐怖と妄想の歴史』p214/ロバート・ウィルキンズ/1990年/原書房)
死後忘れられる恐怖は本当か
このようにイギリスの精神科医は、実際には人々は次々と死後忘れ去られているというのに、「死後忘れられてしまうことに対する恐怖」を強調していますが、今日の私たち(東アジア人)にとっても、この恐怖は真実でしょうか?その前に先立つ「死への恐怖」の方がより一層リアリティーがあるような気がします。
確かに、歴史をヒモ解けば死後の忘れられる恐怖からか、予め膨大な時間と財をかけて造成されたらしいピラミッドや巨大な前方後円墳を見ることができますが、「大抵の人間の場合」には、これらはまったく無関係なモノであり、「孫の代までは覚えられているが、曾孫の代になると忘れられてしまう」ことの方が普通であり、百年もの時間が経つと、故人を覚えている人は誰もいなくなり、忘れられることの方が理に適っているのだと言えます。何しろ百年後とは、いま生まれたばかりの赤ちゃんが、幸運の「人生100年時代」を経て百歳のおじいちゃん・おばあちゃんになるまで待たなければならない、遥かなる未来のような気がします。
その意味では「「死後忘れられてしまうことに対する恐怖」と言われる感情は、今の私たちにとっては希薄になっているようです。
亡き人の記憶を遺された人々に伝える《美しいWeb告別記|記憶葬》
ナウシカが呟くように「生まれ、響き合い、消えてゆく」風な音のような人の生命を、今の時代、遺された人の記憶に留めようとする企みの一つが《美しいWeb告別記|記憶葬》です。
既存の、故人の姓名と遺影を差し替えてスケジュールに合わせて執り行われる葬儀にはない、故人のかけがえのなかった人生の記録を改めて遺族の手で整理し組み立てることで、生きてきた世界に一つだけの告別記がWeb上に生まれます。この生涯の記録を故人の関係者にお知らせし、ご覧になって頂くことで、ひとつの区切りを付けることが出来るのかもしれません。