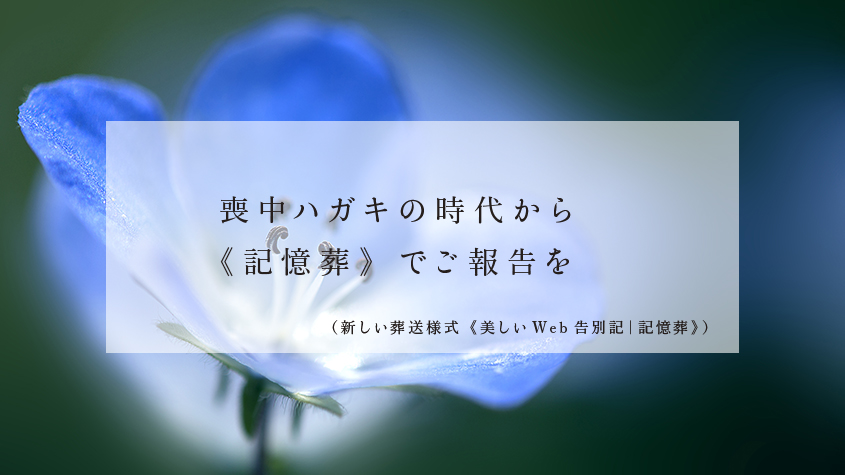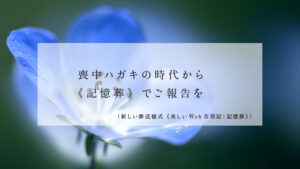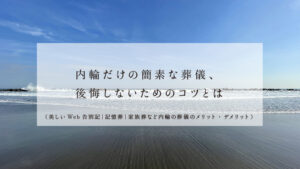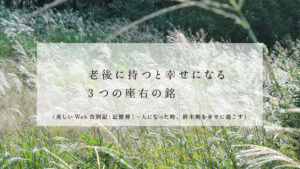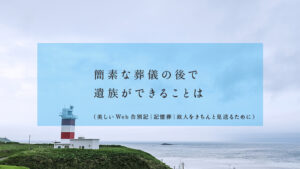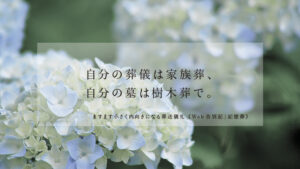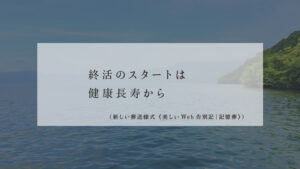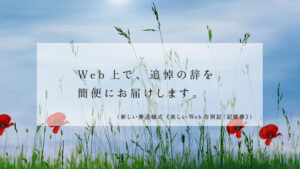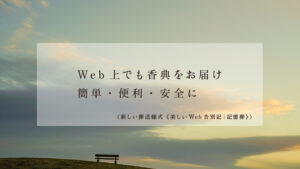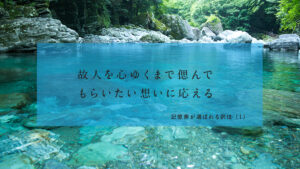亡き人の死を報告し、弔い偲んで頂くための唯一無二のオリジナルなものを作る
家族など身近な方がお亡くなりになると、喪に服していることもお伝えするするために、故人の関係者に届くのが喪中ハガキ。実際に送付した方も多いのではないでしょうか。喪中の風習は、欧米やイスラムの文化圏が広がる中東・アフリカ大陸以外の東アジアに特有のものだと言われています。
*キリスト教では、人は亡くなるとその魂は天国に昇り、幸せになるため、遺族は行動を慎む理由がないようです。
また、これまでは新聞やテレビでの有名人の死亡記事はともかく、一般には喪中ハガキがその独占的な役割を担っていましたが、年賀はがきユーザーの大幅な減少が示すように、snsなどの新しいメディアに人々の関心は移っており、喪中ハガキのユーザーもやがて少数派になるのも、そう遠くないのかも知れません。
これは極めて個人的な想いですが、定型の文面に氏名や年月日、住所を差し替えるだけのこれまでの喪中ハガキでは、余りにも事務連絡的でしかなく、近しい人がお亡くなりになった遺族の悲嘆や、故人を弔い偲ぶ気持ちも見て取ることができないのではないでしょうか。
実際に私の母の死に際しては、私は市販の喪中はがきではなく、かつての母のその人ならではの、生涯のなかでも特に幸せだったほんの一端に触れた一文を添えて関係する人に郵送した経験があります。他にはない唯一無二のものであり、世界に一つしかないハガキでした。(下図)

亡き人の生涯全体を弔うには、オリジナル喪中ハガキが100枚ほど必要に。
このエピソードを素描したオリジナル喪中ハガキ(上図)の刷り出しを見た母の親族は「こんな喪中ハガキは初めてだ」とか「お母さんは幸せ者ですね」など、市販のものに比べると内輪では好意的な印象でしたが、印刷→郵送→届いた人からの反応、という一連のプロセスが一段落した後の想いを一言で表現すると、「故人の、生まれてから晩年までの一生を辿って行こうとすると、このオリジナル喪中ハガキをあと99枚程作る必要がありそうだ。」です。合わせて100枚ほど必要になります。
◎《美しいWeb告別記|記憶葬》>ブログ|死生観のうつろい > 「百年の葬送」でも、いくつかの事例をもとに近現代時代の人の生涯について触れています。詳しくはコチラ
100枚のハガキをまとめてみると《Web告別記|記憶葬》になる。
この「故人の、生まれてから晩年までの一生を辿ってみる」思いを具現化し生まれたサービスが《美しいWeb告別記|記憶葬》です。
《美しいWeb告別記|記憶葬》は、Webサイト上で故人を弔い偲ぶ新しい様式の、追悼のためのWebコンテンツ作成ツールです。以下の11ページで構成されています。
- タイトル(トップページ)
- 喪主ご挨拶
- 遺影写真掲載
- 故人の横顔
- 故人史
- 写真館
- ムービー館
- 追悼文掲載
- 追悼の辞受付
- 香典オンライン受付
- 感謝と御礼
*上記の11ページ中、青色の5ページは任意ページ。作成・非作成はユーザーにお任せのページになります。
これからの葬儀はWeb上でも執り行えます。《Web告別記|記憶葬》
これからは葬儀社に頼ることなく、ご遺族自らの手でWeb上で故人を心から弔い偲ぶ追悼用コンテンツ作成ツール《美しいWeb告別記|記憶葬》を利用して、世界に一つだけの故人を追悼するWebサイトを作成し、故人の関係者に期間限定で公開することができます。
《美しいWeb告別記|記憶葬》は作り方も簡単。あらかじめ用意されたシンプルで上品なデザイン・テンプレートを利用して、最大11ページのレイアウト構成に沿って、故人の写真画像および文章を載せるだけで、Webページが自動で作成されます。(下図は作成例)
下図はWebサイトのトップページにあたる「タイトルページ」の左はユーザーの編集ページ(一部)。①・②・③はユーザーの記入例になります。右はそのWebページ、あらかじめ用意されたシンプルで上品なデザイン上でユーザーの記入結果を自動表示してくれます。

このように、入力内容、入力場所および背景画像の選択などがユーザーにわかりやすいデザイン・テンプレートとして用意され、例えば、当該のタイトル(トップページ)だと作成自体は数分で完了するはずです。(下図はWebページ表示サンプル)

以上のように、従来ともすれば葬送の慣行として行われていた喪中ハガキに代わって、追悼用コンテンツ作成ツール《美しいWeb告別記|記憶葬》を利用することで、亡き人を心から弔い偲んでいただく、世界に一つだけの告別を執り行うこともできます。